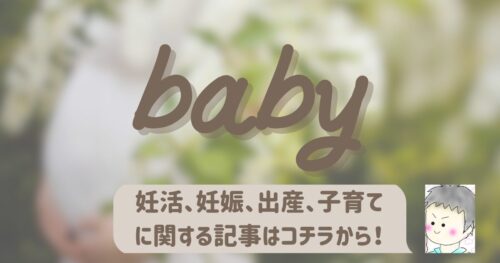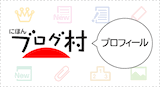この記事では、高校生活3年間を寮で過ごした著者が、実際に感じた寮生活のメリットとデメリットをご紹介していきます。
この記事はこんな人におすすめ
- 寮に入りたいと考えている人
- 行きたい学校は通学が困難
- 親元を離れて学校に通う必要がある人
- 行きたい学校が全寮制の人
- 高校生から生活力を身に着けたい人
この記事を書いた人
・夫婦でブログ運営
・県外の進学高校に進学
・高校は3年間寮で生活
・男子寮・女子寮は併設
・高校は硬式野球部に所属
関連記事もございます。ご参考までに。
-

【この記事だけで完璧!!】高校寮生活で必要なもの35選-あると便利なもの-
学生寮という環境は一般的な一人暮らしとは違います。 この記事では高校3年間を寮で過ごした著者が学生寮生活に必要なもの、不要な場合が多いもの、あると便利なものをそれぞれ紹介していきます。 ...
続きを見る
-

高校生寮生活の実態
こんな方におすすめ 高校の寮生活の実態が気になった人 高校で寮生活を始める必要がある人 子供が寮に通う予定の親御さん 関連記事もございますので、 ...
続きを見る
高校寮生活のデメリット
お金がかかる

寮生活にはもちろんお金がかかります。
参考までに、著者のお世話になった寮では、食費光熱費等全て込みで寮費が35000円でした(親に確認しました)。
公立高校で学校が運営する寮(しかも田舎)だったので、かなり安い方だったと思います。
それでも著者の生まれは裕福な家庭ではなかったので、毎月大きな出費で負担をかけていたと思っております。
寮生活を検討中のご家庭は入る可能性がある寮の値段を事前にチェックしておくのがおすすめです。
併せて、食費も入っているか確認しておきましょう。
馬が合う同居人に当たるかは運次第

寮生活は全くの他人と共同生活を送ることになるわけです。
そのため、全員と気が合うとは限りません。
自分と合う人と一緒になるかどうかは運次第です。
どうしても馬が合わない人と同じ部屋になってしまった時等は先生や友人に相談したり、時には本人と腹を割って話すのも良いでしょう。
規則が厳しい
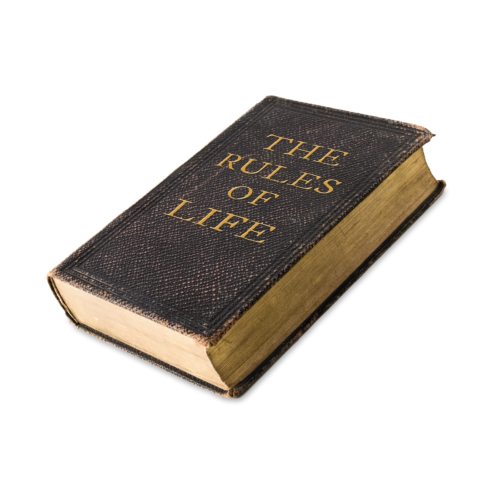
寮はルールが厳しい場合が多いです。
著者がお世話になった寮も例外ではなくルールが厳しかったです。
ざっくり下記等がありました。
- 朝晩の点呼
- 掃除・朝食準備の当番制
- 厳しめの門限
- 勉強時間の設定
- 消灯時間の設定
- 寮生以外は侵入禁止
点呼は遅れたら怒られるし、掃除、朝食準備等ももちろんサボるなんて言語道断。
門限を過ぎた時は窓の開け閉めで警備会社が来るので、物理的に出入りできなくなります(後述します)。
勉強時間は2時間程設定されていました。
その時に舎監の先生が見回りに来るので、机についていないと怒られます。
ちなみに部活で疲れ切った著者は、同居人に

と言い残して勉強時間にベッドでよく寝ていました。
ただ、時々忍び足でやってくる先生がいて、その先生には寝ている事がばれます。

と怒られるなんて事もざらでした。。。
それから、寮生以外は原則侵入禁止でした。
そのため、友人や恋人を寮に呼ぶなんてことはかなりハードルが高いです。
プライベート空間が少ない

著者が住んでいた寮は4人1部屋で、しかも広さも10畳弱くらいでした。
そのためプライベート空間なんてものはほとんど存在しません。
強いて言えば、カーテンによる仕切りが可能なベッドだけがプライベート空間です。
最初は抵抗があるかもしれません。
しかし、住めば都とはよく言ったもので、意外とすぐに慣れます。
高校寮生活中に起きたトラブル
問題行動の連帯責任

寮生活では誰かが問題行動を起こすと、周りの人にも被害が及ぶ事があります。
一つ著者の体験談を例に挙げると、ある先輩が夜の寮を抜け出して学校を退学になるレベルの問題を起こしてしまいました。
それがきっかけで、学校の先生達はより厳しく学生を管理するために門限を過ぎて窓を開けるとアルソックが来るシステムが導入しました。


もちろんアルソックを呼ぶような事があれば、先生にこってり絞られます(笑)
余談ですが、アルソックの方々は本当に優秀です。
著者はうっかり呼んでしまった事があるのですが、駆け付けるまでの時間がめちゃくちゃ短いです。
著者が呼んでしまった時は体感3分くらいで来た記憶があります。
警備会社との契約を考えている人はご参考までに。
盗難

一緒に暮らす仲間を疑いたくはないですが、モノがなくなる、お金がなくなるといったトラブルが実際に在寮中にありました。

びっくりなんやけど・・・
犯人は見つかって退学になったけど。

持ち物の管理はしっかりする必要があります。
現金や貴重品の保持する量はできるだけ少なめにするのがポイントです。
またその一方で、当たり前ですが、人のものは盗らないようにしましょう。
集団感染

寮は共同生活です。
そのため、インフルエンザや風邪等が広がりやすいです。
実際に、同じ部屋の人が全員体調不良になる何てこともありました。
寮では日頃から加湿や手洗いうがいで体調を崩さないように意識する事が大切になってきます。
高校生の時に健康に気を回すのはなかなか難しいですが、、、
高校寮生活のメリット
勉強の相談相手が豊富

感じ方に個人差はあれど、高校生の勉強は難しいです!
そんな中で、勉強面における寮生の一番の強みは、友人だけでなく、先輩や舎監の先生に勉強を相談できる事です。
寮で暮らす友人は一緒にバカ騒ぎするだけでなく、勉強についても一緒に悩む事ができます。


著者の両親は勉強に関しては中学校レベルでつまずいているので、自宅にいては絶対に得られなかったメリットです。

それでも勉強に対して不安がある人には下記のようなオンライン塾がおすすめ。
ポイント
- ビリから慶応合格!有村架純さん主演のビリギャルのモデル塾!
- 心理学を用いた科学的な指導メソッドで生徒一人ひとりのタイプに合わせて指導!
- 講師との対話によるアウトプットで、理解と記憶が深まる!
更に説明会ではそんな坪田塾の指導メソッドがなんと無料で公開されています。
入塾しなかったとしてもその後の学習に役立つ情報が提供されています!
定員も限られているとの事なので、気になる方はぜひお早めに下記のリンクから無料相談を申し込んでみて下さい。
協調性・対人関係能力が磨かれる

寮生活では普通の学校生活だけだと、絡む事のなさそうなタイプの違う人ともうまくやっていく必要があります。
10代の多感な時期に自分とは大きく価値観の違う人と深く交流できる事は、長い人生において大きなメリットになります。
著者は寮で多種多様な人との人間関係の作り方が自然と学べたと感じています。
著者の場合、運動部所属で元気が有り余っているような友人が多かったのですが、学校ではかなり大人しくしている人とも友人になれました。

寮で生活する事で友人の幅が広がって、スクールライフもより一層充実します。
また、著者がお世話になった男子寮はどちらかと言えば体育会系ノリでした。
ですので、ここで①敬語、②元気の良い挨拶が重要と教わり、これらが身に着きました。
これは一例ですが、寮生活では上述のような社会性や礼儀も自然と身に着きます。

自立心・生活力が身に着く

寮で生活する場合、決められた掃除や朝食準備等以外に、自分の家事もしなければなりません。
その結果、自立心と生活力が身に付きます。
社会人になってしまえば当たり前の事かもしれませんが、以下のような事を自然と考えられるようになります。
・そろそろ洗濯しないと着る服なくなるな
・日用品がなくなるから買っておこう


また親から金銭的な援助を受けているとは言え、できる事が増えて1人でも生きていけそう!という自信がつきます。
その他
その他のメリットとしては以下等があります。
その他メリット
- 大人になってからの話の小ネタになる
- 学校の先生とも仲良くなれる⇒オフの先生と話ができます
- 日用品や文房具の相場を意識するようになる
- お金のやりくりが上達する
まとめ
今回の記事では高校で寮に入るメリットとデメリットについて下記の通りご紹介しました。
高校寮生活のデメリット
- お金がかかる
- 馬が合う同居人に当たるかは運次第
- 規則が厳しい
- プライベート空間が少ない
高校寮生活のメリット
- 勉強の相談相手が豊富
- 協調性・対人関係能力が磨かれる
- 自立心・生活力が身に着く
- その他+α
これから寮に入る予定の人、寮に入る事を検討している家族の皆さんの参考になれば幸いです。
⇓⇓関連記事⇓⇓
-

【この記事だけで完璧!!】高校寮生活で必要なもの35選-あると便利なもの-
学生寮という環境は一般的な一人暮らしとは違います。 この記事では高校3年間を寮で過ごした著者が学生寮生活に必要なもの、不要な場合が多いもの、あると便利なものをそれぞれ紹介していきます。 ...
続きを見る
-

高校生寮生活の実態
こんな方におすすめ 高校の寮生活の実態が気になった人 高校で寮生活を始める必要がある人 子供が寮に通う予定の親御さん 関連記事もございますので、 ...
続きを見る